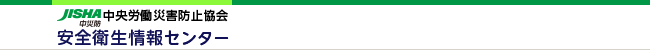
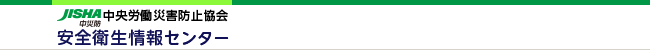
|
別紙 (平成13年4月25日 基発第401号の2により廃止)
| ダイオキシン類に係る作業環境測定及び評価方法 |
|||||||
| 1 | 作業環境測定 作業環境における空気中のダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン及びコプラナーPCBをいう。以下同じ。)の濃度測定を行う場合においては、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に準じた次の方法により行うこと。 |
||||||
| (1) | 測定の頻度 | ||||||
| イ | 6月以内ごとに1回、定期に、実施すること。 | ||||||
| ロ | 施設、設備、作業行程又は作業方法について大幅な変更を行った場合は、改めて測定を行うこと。 | ||||||
| (2) | 測定の時間帯 焼却炉、集じん機その他の装置の運転等の作業が定常の状態にある時間帯に行うこと。 なお、作業場が屋外の場合には、雨天、強風等の悪天候時は避けること。 |
||||||
| (3) | 測定の位置 | ||||||
| イ | 作業場が屋内の揚合 次の測定を行うこと。 |
||||||
| (イ) | A測定の測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上に6メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。 また、A測定の測定点の数は、単位作業場所について5以上とすること。 |
||||||
| (ロ) | B測定は、粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、(イ)に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業の行われる位置において測定を行うこと。 | ||||||
| ロ | 作業場が屋外の場合 粉じんの発散源に近接する場所において、B測淀による測定を行うこと。 |
||||||
| (4) | 空気中のダイオキシン類の温度測定 ほとんどのダイオキシン類が粉じんに吸着していることから、粉じんに吸着しているダイオキシン類の含有率を算出し、空気中の総粉じんの温度にその含有率を乗じてダイオキシン類の濃度を推定することができること。 そのため、併行測定を行い、下記ハのD値を求めること。ここで求めたD値は2回目以降の測定に使用してもよいこと。ただし、作業場の施設、設備、作業工程又は作業方法について大幅な変更を行った場合は、改めて併行測定を行いD値を再度求めること。 |
||||||
| イ | 空気中の総粉じんの濃度測定 空気中の総粉じんの濃度測定は、ろ過捕集方法及び重量分析方法によること。また、試料の採取方法は、ローボリウムサンプラーを用いて、オープンフェイス型ホルダーにろ過材としてグラスファイバーろ紙を装着し、毎分20~30リットルの吸引量とすること。なお、A測定及びB測定のサンプリング時間は各測定点につき10分間以上とすること。 |
||||||
| ロ | 併行測定について | ||||||
| (イ) | 単位作業場所(作業が屋外の場合には、粉じん発生源に近接する場所)の1以上の測定点において併行測定を行って、下記ハによりD値を求め、最大のD値を下記二のダイオキシン類の濃度の決定に用いること。 | ||||||
| (ロ) | 併行測定点での空気中の総粉じんの濃度測定は、(ハ)のサンプリング時間と同じ時間併行して行うこと。 | ||||||
| (ハ) | 併行測定点での空気中のダイオキシン類の濃度測定は、ろ過捕集方法及びガスクロマトグラフ質量分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によること。また、試料の採取方法は、ハイボリウムサンプラーを用いて、毎分500~1000リットルの吸引量とすること。さらに、サンプリング時間は、採じん量が10㎎以上となるようにすること。 | ||||||
| ハ | D値の算出について 併行測定点において求めた「空気中の総粉じんの濃度」及び「空気中のダイオキシン類の濃度」を用いて次の式からD値を求めること。
|
||||||
| ニ | 空気中のダイオキシン類の濃度の決定 空気中のダイオキシン類の濃度は、ハで求めたD値を用いて次式により空気中の総粉じんの濃度から計算することができること。
|
||||||
| 2 | 作業環境測定の結果の評価 作業環境測定の結果の評価は、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79)に準じた次の方法により行うこと。 |
||||||
| (1) | 管理濃度 ダイオキシン類の管理濃度は、2.5pgTEQ/m3とすること。 |
||||||
| (2) | 管理区分の決定方法 | ||||||
| イ | 作業場が屋内の場合 作業環境測定の結果の評価は、単位作業場所ごとに、第1管理区分から第3管理区分までに区分することにより行うこと。なお、第1評価値及び第2評価値とは、作業環境評価基準第3条に従って計算した評価値をいうものであること。 |
||||||
| (イ) | 第1管理区分 第1評価値及びB測定の測定値(2以上の測定点においてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値。イの(ロ)及び(ハ)において同じ。)が管理濃度に満たない場合 |
||||||
| (ロ) | 第2管理区分 第2評価値が管理濃度以下であり、かつ、B測定の測定値が管理濃度の1.5倍以下である場合(第1管理区分に該当する場合を除く。) |
||||||
| (ハ) | 第3管理区分 第2評価値が管理濃度を超える場合又はB測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合 |
||||||
| ロ | 作業場が屋外の場合 作業環境測定の結果の評価は、粉じん発生源に近接する場所ごとに第1管理区分から第3管理区分までに区分することにより行うこと。 |
||||||
| (イ) | 第1管理区分 B測定の測定値が管理濃度に満たない場合 |
||||||
| (ロ) | 第2管理区分 B測定の測定値が管理濃度以上であり、かつ、管理濃度の1.5倍以下である場合 |
||||||
| (ハ) | 第3管理区分 B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合 |
||||||